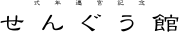特集一
久邇大宮司
インタビュー
式年遷宮元年 ―
求められるせんぐう館の役割
公開日 令和7年10月1日 最終更新日 令和7年10月1日

本サイトでは、「神宮式年遷宮が伝えてきたことを伝える」せんぐう館の役割として、第六十三回神宮式年遷宮に関わる方々からお話を伺ってご紹介します。
第一回目は久邇朝尊神宮大宮司に式年遷宮の進捗とせんぐう館に求められる役割についてお伺いしました。

本日は式年遷宮とせんぐう館の事についてお話を伺いたく存じます。まずは第63回神宮式年遷宮の進捗についてお聞かせください。
昨年(令和6年)4月8日に天皇陛下の御聴許(お許し)を賜り、第63回神宮式年遷宮のご準備が始まりました。そして今年(令和7年)の1月1日にはご準備を取り仕切る組織である神宮式年造営庁を立ち上げました。式年遷宮の事業は、天皇陛下が神宮に寄せられた式年遷宮遂行の思し召しを体し、神宮が主体となって継承しています。
式年遷宮のお祭りが報道などで紹介され、
今年から始まったことが広く知れ渡りました。
はい。5月2日に式年遷宮の最初のお祭りである山口祭、そして木本祭が行われました。山口祭は新宮の御用材を伐り出すに当たり、御杣山(みそまやま)の山の口に坐す神に伐採と搬出の安全を祈るお祭りです。木本祭は御正殿の御床下に奉建する心御柱の御用材を伐採するにあたり、その木の本に坐す神を祀る儀式です。
社殿の造営に用いる御用材を
木曽の御杣山で正式に伐り始めるお祭りも行われました。
6月3日には長野県上松町で御杣始祭(みそまはじめさい)が、5日には岐阜県中津川市で裏木曽御用材伐採式が行われました。二つの神事で伐り出されたヒノキは、御神体をお納めする御器(御樋代(みひしろ))を奉製するための御神木であり、御樋代木と呼ばれます。
まさに「式年遷宮元年」ですね。式年遷宮の紹介をきっかけに神宮へ興味を持たれた方も多いと存じます。
多くの方々のご理解を深めるために必要なことは何でしょうか。
例えば御樋代木は、御杣山の山中で左右に並ぶ二本のヒノキを選び、「三ツ緒伐り」という古式の作法で伐り倒します。トラックで丁重に運ばれ、伊勢に至る沿道では多くの皆様から盛大な歓迎をいただきました。そして伊勢に到着した御樋代木は、内宮ではソリに載せられて五十鈴川を遡る川曳き、外宮では御木曳車に載せられ町中を練り歩く陸曳きという形で、古式のままに神域へ曳き入れられました。
天皇陛下の大御心で斎行されます式年遷宮の伝統は、その時代を生きる多くの方々のまごころとご奉賛で紡がれてきました。また時代の変遷を経ても造営に関わる技術の伝承といったことは変わりがないことを踏まえ、神宮と式年遷宮の「今」を丁寧に伝えることだと思います。
大宮司はよく知人の方を神宮にお招きしていると伺っています。
ご案内の際にはどのようなことを重点的にお伝えしていますか。
知人には神宮の参拝を勧め、できる限り案内に同行して自分の言葉で神宮のことを理解してもらえるよう努めています。
私たちも参拝者と接する機会があれば、神宮のお祭りや匠たちの心と技、神宮の歴史と文化をしっかりと伝えたいと思っています。ですが相手が普段から神宮のことを強く意識していなければ、言葉だけで伝えることには限界があります。
私は時間に余裕を持って行程を組み、できる限り神宮の博物館を観覧して、神宮や式年遷宮のことを学び取ってもらえるようにも伝えています。
両宮へお参りいただくだけではなく、学びの機会を得られる博物館を訪れることが必要とのお考えでしょうか。
神宮には長い歴史とともに蓄積された文化財を持っています。それは先人が伝えてきた尊い考え方を記した書物であったり、または類い希な技術で作り上げた工芸品であったり、或いは神様を崇める人々の心を形にした美術品があります。

外宮域内の「せんぐう館」は、式年遷宮を通じて伝えられてきた日本の伝統や
精神文化を次の世代に継承することを目的とする博物館です。
展示資料である御装束神宝の調製工程を伝える品々や外宮正殿の原寸大模型は、匠たちが同じ素材、同じ技術を用いて忠実に再現した本物です。最近では仮想現実の技術を取り入れた体験型施設が人々の関心を高めていますが、せんぐう館は本物を直に感じ取ることができるので貴重だと思います。
せんぐう館はここ数年来館者が増加しています。昨今のインバウンド効果によって外国人の姿は以前より増えていますが、それ以上に若年層のグループやご家族連れの来館者が目立ちます。
知人を案内したときにも同じ事を思いました。本物だからこそ伝わる、匠たちの精巧な技と神様に捧げるという心が、国境や世代を超えて理解に繋がっているのだと思います。せんぐう館の来館をきっかけに、日本文化への興味・関心が広がるのかもしれません。
せんぐう館では、神宮や式年遷宮の祭典と歴史、社殿の構造を15分程度で説明する展示ガイドを1日6回
(10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00)原寸大模型の前で常に行い、職員が参拝者の目線に立って共感できる時間を設けています。
職員が多くの参拝者に寄り添うことで、深い理解に繋がることを期待しています。

最後にせんぐう館の活動について、今後期待することをお聞かせください。
式年遷宮の機運の高まりに応える企画の充実が求められます。単なるイベント告知として展覧会を行うのではなく、式年遷宮がわが国の伝統的な文化の継承に寄与している意義を伝えてほしいと思います。